サステナビリティ情報開示の浸透と保証業務義務化に向けたビジョン―国際的動向と日本基準の進展
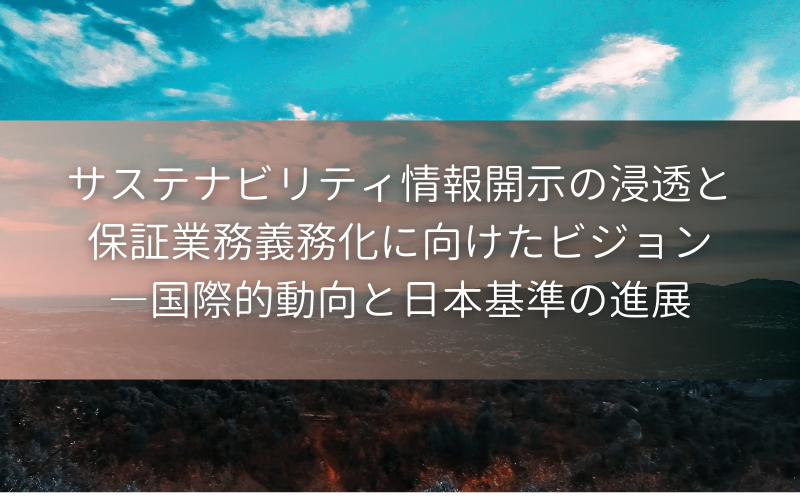
2025年3月の日本版サステナビリティ基準(S1,S2)の確定をうけ、これから企業に求められるサステナビリティ開示・保証対応について、国際的な動向をふまえながら今後の進展について解説します。
JFAEL特別フォーラムと個別論点を扱うセッション①、セッション②を開催いたします。
<5/26追記:セッション①(6/17開催)、セッション②(7/9開催)の開催情報を記載いたしました。>
【JFAEL 特別フォーラム】
≪後援≫
日本公認会計士協会
≪開催日≫
2025年5月20日(火)
≪タイムテーブル≫
11:00-11:10 開会のことば(理事長:手塚正彦)
11:10-12:10 【特別フォーラム①】「日本企業に期待されるサステナビリティ情報開示への取組み」
小森 博司 氏(国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)理事)
13:00-14:30 【特別フォーラム②】「日本におけるサステナビリティ開示および保証の展望」
野崎 彰 氏(金融庁企画市場局 企業開示課長)
14:45-16:15 【特別フォーラム③】「サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の概要と公開草案からの主な変更点」
中條 恵美 氏(サステナビリティ基準委員会 常勤委員)
16:15-16:20 閉会のことば(日本公認会計士協会 会長:茂木 哲也 氏)
16:20-17:00 登壇者・会場参加者によるネットワーキング
【セッション①】
≪開催日≫
2025年6月17日(火)
①-1 ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」の解説
講師:中條 恵美 氏(サステナビリティ基準委員会 常勤委員)
①-2 テーマ別基準第1号「一般開示基準」および第2号「気候関連開示基準」の解説
講師:小西 健太郎 氏(サステナビリティ基準委員会 ディレクター)、桐原 和香 氏(サステナビリティ基準委員会 ディレクター)
【セッション②】
≪開催日≫
2025年7月9日(水)
サステナビリティ情報の保証業務義務化によるインパクト
講師:関口 智和 氏(有限責任あずさ監査法人 常務執行理事/サステナブルバリュー本部 副本部長/会計・開示プラクティス部長 パートナー)、斎藤 和彦 氏(KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役)
実施形態
ハイブリッド(会場参加またはライブ配信)+アーカイブ配信※ハイブリッド(会場参加またはライブ配信)にお申込みいただくとアーカイブ配信も視聴いただけます。アーカイブのみご希望の方もこちらからお申込みください。
※会場参加のお申込みは会場のお席が埋まり次第締め切りとなります。ご希望の方はお早めにお申込みの上、メールにてご連絡ください。
※ライブ配信はZoomウェビナーを使用して配信いたします。視聴用URLはZoom (no-reply@zoom.us)から配信されます。
CPDについて
●単位付与条件 会場参加:受付にてCPDカード登録・全時間の受講、ライブ配信:受講後のアンケート回答・全時間の受講※単位数は各回によって異なりますので個別プログラム詳細をご覧ください。
※日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けているセミナーがございます。対象セミナーにつきましては個別プログラム詳細をご覧ください。
※CPD単位取得希望の方は、アンケートに研修登録番号を必ずご記入ください。未記入の場合、CPD単位の付与ができない場合があります。
※アーカイブ配信での受講の場合は単位付与対象外となります。「自己学習」としての利用は可能ですので、ご希望の方はご自身で単位の申告をお願いいたします。
※単位認定研修についての詳細はこちらをご確認ください。
実務補習単位について
●単位付与条件 会場参加:受付にて署名簿への記入・全時間の受講、ライブ配信:セミナー全時間の受講、受講後のアンケート回答※単位数は各回によって異なりますので個別プログラム詳細をご覧ください。
※アーカイブ配信での受講の場合は単位付与対象外となります。
受講料
会員
無料※法人会員:5口未満の会員は1口6名まで、5口以上加入の会員は1口3名まで無料、超過した場合は超過人数1名あたり各回5,000円(税込)
非会員
各回あたり15,000円(税込)※特別フォーラム①~③はそれぞれ別の回となります。
※開会・閉会のご挨拶はそれぞれ特別フォーラム①および③に含まれます。
※セッション①-1と②-2はそれぞれ別の回となります。
申込期限
日程
【JFAEL 特別フォーラム】
2025年5月20日(火)11:00~17:00
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
【セッション①】
セッション①-1 2025年6月17日(火)13:00~14:00
セッション①-2 2025年6月17日(火)14:15~16:15
アーカイブ配信期間:2025年6月30日(月)~2025年12月31日(水)
【セッション②】
2025年7月9日(水)14:00~15:30
アーカイブ配信期間:2025年7月22日(火)~2025年12月31日(水)
申込期限
会場参加・ライブ配信:各開催日の3営業日前まで アーカイブ配信:2025年12月20日(土) ※下記[マイページをお持ちの方]よりお申込みの方へのご案内 新システムの動作により、本シリーズの他セミナー回をすでにお申込みされている場合に[申込済]と表示される事象が発生しております。そのため、MYページ内[セミナーを探す]にて「サステナビリティ情報開示の浸透と保証業務義務化に向けたビジョン」と検索の上、ご希望のセミナーをお選びいただきお申し込みください。大変お手数お掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
プログラム
※上記[マイページをお持ちの方]よりお申込みの方へのご案内
新システムの動作により、本シリーズの他セミナー回をすでにお申込みされている場合に[申込済]と表示される事象が発生しております。そのため、MYページ内[セミナーを探す]にて「サステナビリティ情報開示の浸透と保証業務義務化に向けたビジョン」と検索の上、ご希望のセミナーをお選びいただきお申し込みください。大変お手数お掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【特別フォーラム】開会のことば
2025年5月20日(火) 11:00-11:10
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
手塚 正彦

1985年 東京大学経済学部卒業
2002年 中央青山監査法人 代表社員就任
2005年 同法人 理事就任
2006年 同法人 理事長代行就任
2007年 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 社員就任
2016年 日本公認会計士協会 監査・保証、IT担当常務理事就任
2019年 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 退所
2019年 日本公認会計士協会 会長就任(7月22日)
【特別フォーラム①】日本企業に期待されるサステナビリティ情報開示への取組み
2025年5月20日(火) 11:10-12:10
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の議論が行われる中、今年3月にSSBJ基準が確定した。IFRSS1およびS2と高い整合性を有する基準策定を目指した議論に敬意を表するとともに、金融庁のRoad mapに基づき、今後の我が国における法制化に向けた検討が進むことを期待したい。一方、欧州のEU Omnibusを含め、従来とは異なる議論が起きていることも事実である。このような複雑な状況ではあるが、グローバルでビジネスを展開し、世界中の投資家の投資対象である日本企業のサステナビリティ情報開示について、S1およびS2の議論も交え、改めて認識を深める機会となれば幸いである。
CPD単位数:1.0単位 研修コード:2301
※本セミナーは日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けています。
実務補習生単位数:1.0単位
小森 博司 氏

1979年埼玉銀行(現りそなホールディングス)入行。1990年住友信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社し、証券代行部で信託銀行として初のIR・SRコンサルティングサービスを立ち上げ、特に外国人機関投資家と日本企業との対話の仲介に注力。2015年、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に採用後、市場運用部次長、スチュワードシップ推進課ヘッドとしてGPIFのスチュワードシップ活動およびESGの取組みを推進。PRI Japan Advisory CommitteeのChairおよびPRI Asset Owner Advisory Boardメンバー、CA100+ Asia Advisory Boardメンバー等に就任し、国内外での講演および寄稿多数。2022年3月GPIF退職後、9月より現職。国際大学修士(国際関係学)。
【特別フォーラム②】日本におけるサステナビリティ開示および保証の展望
2025年5月20日(火) 13:00-14:30
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
サステナビリティに関する取組が企業経営の中心的な課題になるとともに、投資家が中長期的な企業価値を評価する観点から、サステナビリティ情報の開示によって企業経営を可視化することへのニーズが高まっている。
本セミナーは、今後、各企業がサステナビリティ情報開示の充実化を図るにあたっての参考にしていただくことを目的とする。まず、サステナビリティ情報開示及び保証に関する国内での議論の動向を概観する。その上で、金融庁が公表している、令和6年度の有価証券報告書レビューにおいて識別された課題やその対応にあたって参考となる開示例集について説明を行う。また、「記述情報の開示の好事例集2024」に基づいて、投資家・アナリスト・有識者が期待するサステナビリティ情報の開示のポイントや、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄にかかる主な好事例の紹介を行う。
CPD単位数:1.5単位 研修コード:2301
※本セミナーは日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けています。
実務補習生単位数:2.0単位
野崎 彰 氏

2000年金融庁入庁。経済協力開発機構(OECD)シニア・ポリシーアナリスト、金融庁総務企画局政策課総括企画官、企画市場局企業開示課開示業務室長、総合政策局組織戦略監理官兼企画市場局フィンテック室長、内閣官房参事官兼デジタル庁参事官を経て、現職。
【特別フォーラム③】サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の概要と公開草案からの主な変更点
2025年5月20日(火) 14:45-16:15
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
2025年3月にサステナビリティ基準委員会より、我が国最初のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表されました。SSBJ基準は、金融商品取引法の枠組みにおいて適用されること、特にグローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業)が適用することを想定して開発が行われており、有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において検討が行われています。
本セミナーではSSBJ基準の概要と公開草案に寄せられたコメントへの対応、ISSB基準との違いなどを解説します。
<ポイント>
・SSBJ基準の概要
・公開草案に対して寄せられたコメントとその対応
・SSBJ基準とISSB基準の違い
・SSBJ基準の適用を支援する取組みと今後の対応
CPD単位数:1.5単位 研修コード:2301
※本セミナーは日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けています。
実務補習生単位数:2.0単位
中條 恵美 氏

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー、日本公認会計士協会 理事(企業会計企業情報開示担当)を経て2022年より現職。
サステナビリティ基準委員会委員としてSSBJ基準の開発に携わる。
【特別フォーラム】閉会のことば
2025年5月20日(火) 16:15-16:20
アーカイブ配信期間:2025年6月3日(火)~2025年12月31日(水)
茂木 哲也 氏

1990 年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業
2002 年 5月 新日本監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人)社員(現パートナー)
2010 年 8月 日本公認会計士協会会計制度委員会 委員長
2013 年 7月 同協会 理事(監査保証・業種別 協力理事)
2016 年 2月 新日本有限責任監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人)経営専務理事
2019 年 7月 日本公認会計士協会 常務理事(総務、地域会、地域活性化、渉外担当)、同協会東京会 副会長(特命担当)
2022 年 6月 EY 新日本有限責任監査法人退所
2022 年 7月 日本公認会計士協会 会長就任(現任)
【セッション①-1】ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」の解説
2025年6月17日(火)13:00~14:00
アーカイブ配信:2025年6月30日(月)~2025年12月31日(水)
2025年3月にサステナビリティ基準委員会より、我が国最初のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表されました。有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において検討が行われていますが、現行制度においても、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄において任意にSSBJ基準を適用して開示することが考えられます。
前半ではサステナビリティ関連財務開示を作成し報告するにあたって基本となる事項を定めたユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」の概要とISSB基準との違いなどを説明します。
CPD単位:1.0単位 研修コード:2301
※本セミナーは日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けています。
実務補習生単位:単位付与対象外です。
中條 恵美 氏

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー、日本公認会計士協会 理事(企業会計企業情報開示担当)を経て2022年より現職。
サステナビリティ基準委員会委員としてSSBJ基準の開発に携わる。
【セッション①-2】テーマ別基準第1号「一般開示基準」およびテーマ別基準第2号「気候関連開示基準」の解説
2025年6月17日(火)14:15~16:15
アーカイブ配信:2025年6月30日(月)~2025年12月31日(水)
2025年3月にサステナビリティ基準委員会より、我が国最初のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表されました。有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業及び適用時期等については、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において検討が行われていますが、現行制度においても、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄において任意にSSBJ基準を適用して開示することが考えられます。
後半では、テーマ別基準第1号「一般開示基準」および第2号「気候関連開示基準」の概要を4つの構成要素(戦略、ガバナンス、リスク管理、指標・目標)それぞれを対比しながら解説するとともに、ISSB基準との違いなどを解説します。
CPD単位:2.0単位 研修コード:2301
※本セミナーは日本公認会計士協会の社外役員推奨研修として認定を受けています。
実務補習生単位:単位付与対象外です。
小西 健太郎 氏

企業会計基準委員会 専門研究員、日本公認会計士協会 企業情報開示専門委員会 専門委員を経て2022年より現職。PwC Japan有限責任監査法人 パートナー。
サステナビリティ基準委員会ディレクターとしてSSBJ基準の開発に携わる。
桐原 和香 氏

企業会計基準委員会 専門研究員を経て、2022年より現職。㈱日立製作所より出向。
サステナビリティ基準委員会ディレクターとしてSSBJ基準の開発に携わる。
【セッション②】サステナビリティ情報の保証業務義務化によるインパクト
2025年7月9日(水)14:00~15:30
アーカイブ配信:2025年7月22日(火)~2025年12月31日(水)
最近、国内外において、サステナビリティ情報の開示の拡充に向けた動きが拡大している。特に、EUでは2024年度より、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づいてサステナビリティ情報の開示が制度化されており、同時に保証業務の義務化もスタートしている。
また、日本でも、金融庁が金融審議会に設置した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」でサステナビリティ情報開示の制度化に向けた方向性について検討がされているほか、「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」において保証のあり方について検討が進められている。
本講演では、こうした背景を踏まえ、サステナビリティ情報の保証に関して、制度動向や最近国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表されたISSA5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」を踏まえつつ、基本的な概念を説明したうえで、実務上の課題について掘り下げていく。
CPD単位:1.5単位 研修コード:3003
実務補習生単位:単位付与対象外です。
関口 智和 氏

有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事/サステナブルバリュー本部 副本部長/会計・開示プラクティス部長 パートナー
1995年に朝日監査法人に入所。 2004年より、金融庁総務企画局企業開示参事官室(現企業開示課)において国内外の会計・監査制度の立案に携わったほか、2009年より企業会計基準委員会(ASBJ)で研究員、常勤委員として従事し、日本の会計基準の開発や国際的な会計基準に対する意見発信を担った。また、2009年から2014年まで、国際監査・保証基準審議会(IAASB)のボードメンバーとして国際的な監査基準の開発等に関与した。
現在、会計・開示プラクティス部長として会計・開示に関する品質管理の責任を担うとともに、サステナブルバリュー本部 副本部長としてサステナビリティ関連業務を担当している。加えて、2023年9月より、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のTransition Implementation Groupのメンバーに加入し、KPMGネットワークの代表を務めている。
斎藤 和彦 氏

株式会社富士通総研を経て2002年4月、朝日監査法人に入所。2004年4月、あずさサスティナビリティ株式会社(現KPMGあずさサステナビリティ株式会社)設立に伴い、出向。化学、エネルギー、鉱山・非鉄金属、製薬、運輸など、幅広い業種のサステナビリティレポートの第三者保証業務のほか、環境デューデリジェンス、環境・安全コンプライアンス監査、その他関連するアドバイザリー業務に携わっている。
会場・受講方法
会場参加_東京金融ビレッジ
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5階
アクセスマップはこちら
備考
アクセス:大手町駅から直結(東京メトロ丸ノ内線A1出口(鎌倉橋方面)が最寄り)
大手町駅には、東京メトロ丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線、都営三田線が乗り入れています。
ライブ配信
お申し込み後、前日までにお申し込み頂いたメールアドレスに視聴URLをお送り致します。
また、ライブ配信ではZoomを利用します。
事前にこちらのマニュアルをご確認ください。
アーカイブ配信
アーカイブ配信は、ライブ配信と同じ映像を後日再配信するものです。
配信開始いたしましたら、ご案内メールをお送りいたします。
配信期間は本ページ内の日程欄をご覧ください。
ご参加にあたってのお願い・注意事項
●受講者お一人ずつ異なるメールアドレスでお申込みください。共有メールアドレスでのお申込みは受講管理の都合上お受けできかねます。
●荒天、天災、交通災害、通信回線障害、講師の急病その他やむを得ない事情により、セミナー延期、中止、中断させていただくことがあります。
●本セミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロード、また資料の無断転用は固くお断りいたします。
●受講アカウントの共同利用は固くお断りいたします。必ず受講者ごとにお申込みください。講義映像をスクリーン等に投影し、複数人で視聴するような行為もご遠慮ください。
●本講座の記録及び広報のため、本講座の様子を撮影又は録画し、参加者の方を特定しない形で利用をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
●本講座受講者において、迷惑行為及び、進行の妨げとなる行為(不規則発言など)が行われた場合には、強制的に退出させる場合があります。
 役員・会計
役員・会計